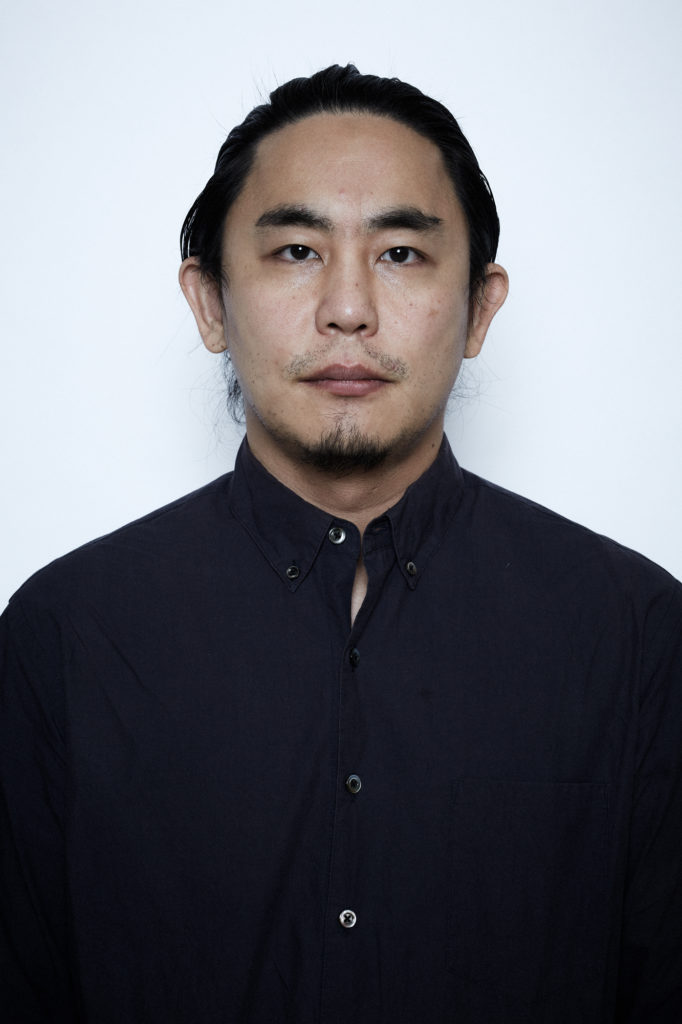日本におけるクラウドファンディングの先駆けである「MotionGallery(モーションギャラリー)」は、日本の表現における数少ない希望の星だ。今年、同プラットフォームを通じて様々な映画人が参加を呼びかけた「ミニシアター・エイド基金」が、SNS上を中心に大変な熱気を帯びていたことを覚えている人も多いだろう。また、ただいま話題沸騰中の映画「スパイの妻」で脚本を手がけた濱口竜介監督が、業界の中でよく知られる存在から映画界のニュースターに上りつめるきっかけを作ったのも、この「MotionGallery」である。そして、その旗振り役をつとめるのが、今回のスミス・大高健志さんだ。
大高さんは、商業主義の中で軽視されがちな存在に対して、その後の成長路線も視野に入れながら、プラットフォーマーの立場から粘り強く支援を続けている。そんな「オルタナティブ=主流ではないもの」に対する強い思い入れには、どんな背景が眠っているのだろうか。ここでは、その半生と考えを紐といていく。
バッドエンディングのSF作品が開いた扉
その日、中学2年生の大高さんは、「いま観るの、逆に面白そうじゃない?」と冷やかしのつもりで友達とドラえもんの映画を観るはずだった。しかし、そのチケットが予想外に売り切れており、そのかわり別で上映していた『12モンキーズ』(95年、テリー・ギリアム監督)を観ることにした。本作は、いわゆる映画好きから評価の高い一風変わったSFもの。これまで映画とは無縁だった大高さんにとっては、そもそも「バッドエンディングである」こと自体が驚愕だった。
「それまでアートやカルチャーにそこまで興味を持っていたわけでもなく、映画といえばハリウッド超大作しか知らない。こんなに皮肉のきいたバッドエンドは一度も体験したことがなかった。だけどそれが露悪的でもない……こういうものを映画で表現していいんだと、自分の中での“映画”が拡張されました」
大高さんは『12モンキーズ』をきっかけに、映画の世界へ本格的にのめりこんだ。そのころ観ていたのは、主に『メメント』『アメリカン・ヒストリーX』のような中規模のアメリカ映画。監督では、クリストファー・ノーラン、クエンティン・タランティーノのような、今でこそ大物だが当時は新進気鋭の扱いを受けていた人たちを熱心に追いかけていた。また、そこからサリンジャーなど小説も読み始める。ゲームも大好きだった。
「それもプレイステーションではなく、僕はセガサターンとドリームキャストで遊んでいました。今思えば、ですが、やっぱりマイナーなものが多い(笑)。無意識的にオルタナティブなものが好きなのかもしれません」
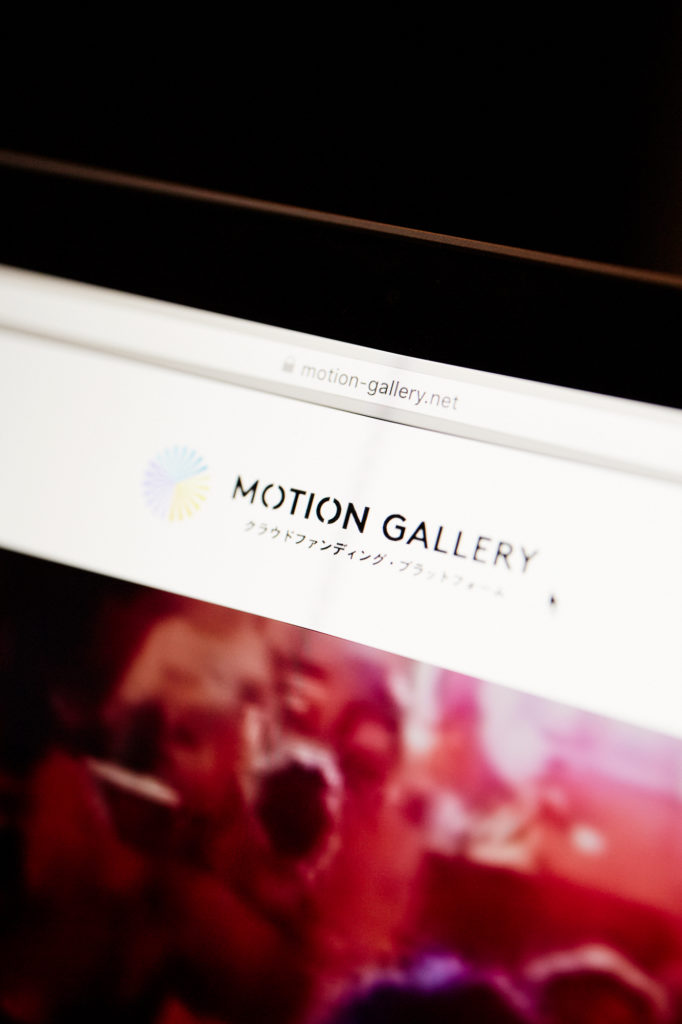
アカデミズムへの傾倒がもたらした視点
中高と映画を観続け、大学では政治哲学を専攻した。自身が傾倒していた「オルタナティブ」「カウンター」と呼ばれるものが、社会の中でどう位置付けられているのか。その精神性や仕組みを解きあかしてみたい、という知的好奇心に突き動かされていた。大高さんは哲学に出会ったことで、自分の考えに対してまずは疑ってかかるという習性を身につけることができたという。
それはアートや禅の体験から得られるものにも似ていて、世の中の事象や思想を相対化して眺めることで、自身をフラットに保つことができた。
「大学時代、大半の人たちが何かしらを得よう、生産的であろうと猛進している中で、自分はひたすら文献を読んだり映画をあさるように見ているだけ。僕は多数派がいる場所から一歩引いて眺めてしまう癖があるんですよね」
この話を聞くと、大高さんが監督やカメラマンではなくプラットフォーマー/プロデューサーの立場から映画に関わっている事実が、まさに必然に思える。もちろん「映画」に対してエモーショナルな思いは持っているが、自身の趣味嗜好を世に打ち出すのではなく、世の中に不足している「王道以外のもの」をひとつひとつ補っているような作業。これは、いわゆる自己表現とは異なる位相にある、映画業界の健全性を保つために必要不可欠な行為だ。
さて彼は大学時代、アカデミックな世界に対する興味を強く持つようなり、そこから現代アートに入れ込むようになった。
「映像文化論というゼミがあったので、てっきり映画を学べるものだと思って入ったら、メインの題材が写真で。うわ、騙された、と思いつつ、課題でドイツのベッヒャー派を扱った写真展に足を運んだんです。今まで僕は、アラーキーの写真とかを見ても『なんかすごい』っていうだけで、ロジックとして落ちてこなかった。でも、その時にはじめて見たベッヒャー派の写真は構築的でロジカルなものだったので、初めて自分が現代アートと対話するきっかけを得た気がしました」
ただ、アカデミズムをどんどん突き詰めていくと、逆にその限界にも意識的にならざるをえない。当時、ワンフレーズ・ポリティクス(政治家がインパクトのある分かりやすい一言で有権者の支持を得ようとする政治手法)の力が増していくに従って、それが正しい・間違っているに関わらず、自分が持っているアカデミックの文脈では現実的に闘いようがないと、ある時から大高さんは感じてしまった。
大高さんが志向していた「自由主義」の本質は、「自分の頭で考える」ということ。そこへたどり着くためには、アカデミックにロジックで訴えるのか、アート表現によって訴えるのか。彼は後者の道を選び、給料の良い外資系コンサルティングファームで働きながらお金をためて美大に入り直そうと考えた。
全てはフィールドワーク
「コンサルの仕事では、自分のロジックではなく他人のロジックの中で解決策を構築する基礎を学びましたね。三ヶ月ごとに上司もクライアントも変わるので、毎回ゼロ地点に戻して、またすぐにキャッチアップすることをやり続けなきゃいけないんです」
大高さんはここでも必死に働きながら、どこかフィールドワーク的な、俯瞰した視点を持っているようにみえる。本人いわく、それは「いろんなことを知りたいっていう気持ちが強いから」だという。アートにせよビジネスにせよ全身全霊をかけている人がいる中で、自分はそのラインに乗っかれない。であれば、それぞれの分野の論理を当事者の立場から体得できれば、両極の世界をつなぐハイブリットな人材になれるんじゃないかと踏んでいた。
会社は予定通り3年で退職。東京藝術大学大学院へ入学し、短期交換プログラムではフランスの名門映画学校であるFEMIS(フェミス)とも交流した。そこで日本とフランスにおける構造の違いを目の当たりにする。日本では、大高さんのようにビジネスエリートから芸術の世界へ足を踏み入れると「ドロップアウト」だと揶揄されることが多いが、FEMISには外務官僚やコンサルファームを経て「やっと念願かなって」入学してくるような人がいる。
また、同校を卒業すれば大半は映画業界で職を得ることができるし、自分の映画を撮る機会ももらえる。しかし、日本では卒業から10年後に1本撮ることができればまだ良いほう。あまりに環境が違いすぎた。
「じゃあ、ハイブランド戦略で戦っているフランスを参考にして、日本の文化行政を変えられるかというと、それは日本人の共通認識を根底から変えることと同義なので難しい。一方で、アメリカのように超巨大なエコシステムの中で若手が自然に起用されることも期待できない。であれば、日本はお客さんに支えてもらうしかないんじゃないかと。それも、消費ではなく文化投資の観点で、『制作日誌が見られます』みたいなところから作品や監督に興味を持ってもらえるかもしれない。そこから、クラウドファンディングの発想にたどり着きました」
現在、大高さんが主宰するクラウドファンディングのプラットフォーム「MotionGallery」は、市場経済のオルタナティブとしての役割をはたしている。立ち上げ当初からジャンルは、活動の指標が市場経済的ではないクリエイティブ系やまちづくりに絞った。

大高さんがプロデュースを手がけた映画『鈴木さん』は、東京国際映画祭で観客賞にあたる「東京プレミア2020」に選出。写真は大高さん提供。©2020 TIFF
そもそも、あらゆる表現の価値は定量化できない。100万人が触れて一瞬は感動するものの数分で忘れてしまうものか、たった10人しか体験していないけれどその人生を180度変えてしまうものか。それでもあえて数値化するならば、作品の価値は「作品に触れた人の数×感動の深さ」で測るべきだ、と大高さんはいう。映画を例に出すと、映画館のチケット料金は全国一律なので、作品の価値をアピールし次につなげるためには、「数」をとりにいくしかない。しかし、クラウドファンディングであれば、応援の度合いをオーディエンスが表現できる。極論、30人の応援で合計金額が1億円ということもありうる。
「今年、MOTIONGALLERYでコレクターを募集した入江悠監督の『シュシュシュの娘』という作品に、1000万円以上(11,923,001円)が集まったんですよね。個人的なひとつの目標として、中規模予算の作品をクラファン発で作ることがあったので、この作品へのリアクションが本当に楽しみで。また、本作品はミニシアターでしか上映しないと決めているので、コロナ禍で全国のミニシアターが苦境に立たされている状況の中では特に意義がありました」
今、何を支えるべきなのか
今年、コロナ禍の影響で廃業の危機に見まわれた小劇場を救うために、映画監督の深田晃司・濱口竜介が発起人となり、同サイト内で「ミニシアター・エイド基金」が立ち上がった。こちらは3億円以上を集め、実際に多くの場所が救われただけでなく、ミニシアターの存在意義が全国に拡散されるきっかけとなった。
「もう経済的な効率性の時代じゃないよね、と言われつつ、むしろ近年はその風向きが強くなっています。コロナ禍のような困難な時期にあっても、何とか耐えしのんで多様性を担保しつづけること、僕らはそのためのインフラを作っているじゃないかという思いがあります。もちろん、個人的にはメジャーなものが嫌いなわけじゃないし、インディペンデントだから観にいく、ということもない。ただ、放っておくと傾いてしまう方をサポートしている、という意識です」
現在は、ポッドキャスト番組「MOTION GALLERY CROSSING」や、自身もキュレーターの一人として参加している「さいたま国際芸術祭2020」(今年11月15日で終了)などを通して、プラットフォーマーとしてだけはなくプレイヤーとしても、文化の多様性を世に打ち出している。日本の素晴らしきオルタナティブが、今日も生き延びていられるように。

さいたま国際芸術祭2020に関わった主要メンバーたちと。写真は大高さん提供。