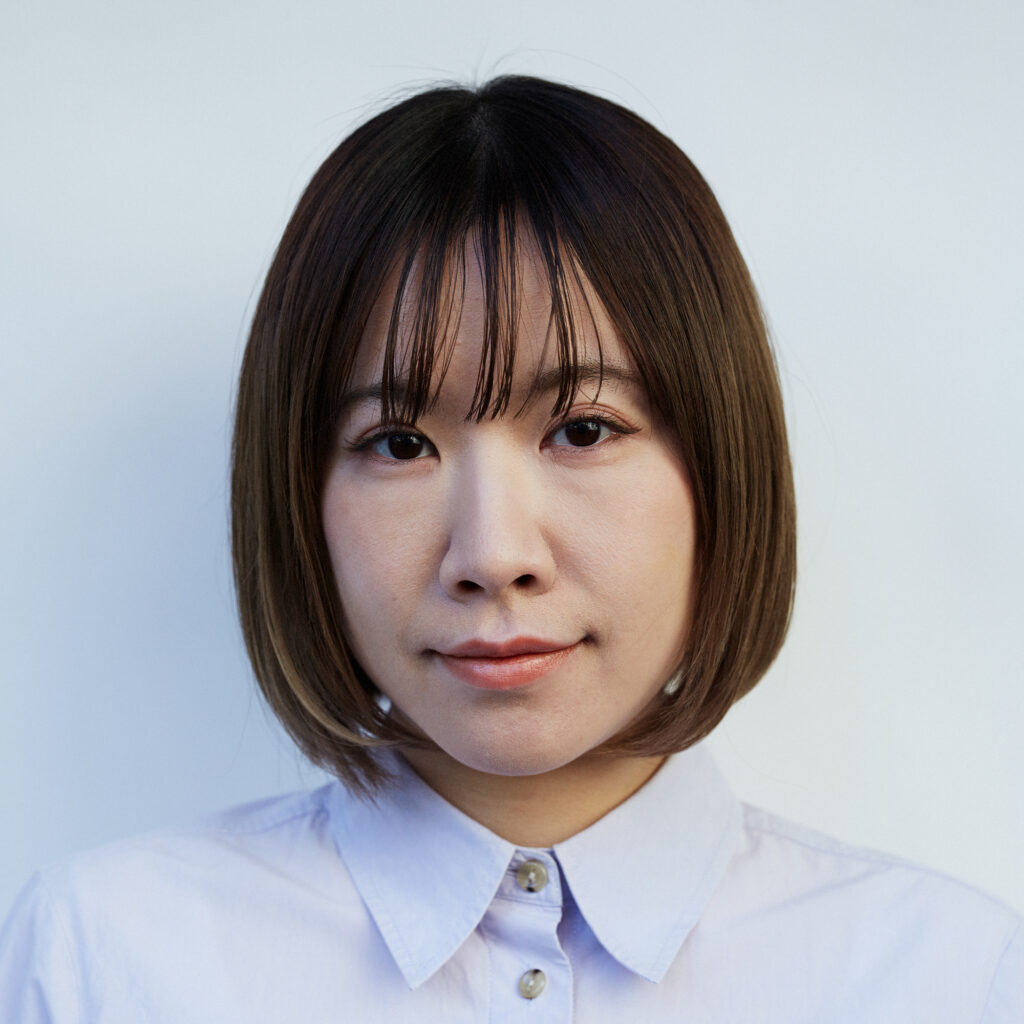今回のスミスは、「知的でかっこいい大人」を目指す女性に向けたランジェリーブランド「タイガーリリートーキョー」を手がける起業家の九冨里絵さん。これまで日本の女性下着といえば、分厚いパッドが入ったブラジャーや派手な配色のものしかなく、そこに紐づく女性像自体にも多様性がなかった。その中で、彼女のブランドは「胸をあげて、寄せて、盛る」という古い常識を捨て去り、「自分自身が心地良さを感じられること」をコンセプトに据えている。さらに、そうやって女性が自分らしくある姿こそが、新たな「美」のスタンダードになる。そこには、社会全体に対する強いメッセージも秘められているのだ。
彼女の姿勢は、ミレニアル世代およびZ世代の女性から絶大な支持を受けているが、事業のアイデアは、子供のころ感じたある疑問から生まれたという。彼女の遍歴を追いながら、その核にあるパーソナリティに迫る。
全ては幼少期に感じた疑問から
九冨さんは子供のころから手先が器用で、小学校に入ると自らパターンをひいて洋服を作りはじめた。きっかけは、デザイナーを夢見る主人公・幸田実果子の奮闘を描いた矢沢あいの漫画『ご近所物語』。また、当時読んでいた『ちゃお』や『なかよし』などの漫画本の付録には、裁縫セットのようなファッショングッズがよくついていたので、早い時期からDIYなものづくりに触れていた。
一方、学校では自他共に認める優等生で、学級委員長を務めたことも。心の中では「クリエイティブなことがしたい」「早く大人になりたい」と考えていたが、それを表立って言うことはしなかった。元来大人しい性格で、そのぶんまわりをじっと観察していたタイプだという。
「今でも周りの人たちを勝手に分析しちゃう癖があって。すごく嫌がられるんですけど(笑)。逆に私はみんな自然とやっていることだと思い込んでいました」
子供らしからぬ落ち着きをみせていた彼女は、身体の成長も早かった。小学6年生になると身長が150センチを超えてきて、見た目はほとんど大人。しかし、ファッションの選択肢といえば、「子供はとりあえずこれ」という子供服やランドセルしかなく、下着に関してはスポーツブラのみ。道を歩いていてふとガラス窓に映った自分のランドセル姿があまりにチグハグで、母親にも苦情を伝えたが、その時点では解決のしようがなかった。


「モンべべリリー」のイメージビジュアル。従来のように下着だけでなく、モデルやシチュエーションの空気感を含めた「ファッション」全体を捉えているのが特徴的。*写真は九冨さん提供
「中学に入るとその違和感は増すばかりでした。『14〜5歳の女の子向け』というカテゴリー自体、かつてはラブリーか、ギャルっぽい派手なブランドしかなかったんです。そのときに、理想のものがないなら自分で作るしかない、と思いましたね。自分のブランドを立ち上げることは、15歳の時点で決めていました」
そんな彼女の考え方に大きな影響を与えたのが、下着デザイナー・鴨居羊子による自伝『わたしは驢馬に乗って下着をうりにゆきたい』。彼女はもともと新聞記者で、社会に対して様々な課題を感じる中で、特に女性の立場や感情のあり方にフォーカスした活動を行なっていた。
彼女自身、自分の給料で弟と母親を養っており、当時では珍しく「社会進出を果たした女性」という存在。ただ、本著を読んでみると、こと女性下着に関していえば、実は女性進出が遅々として進まない状況と同じく、今もあまり問題の本質は変わっていないように感じた。その志を受け継ぐ、という意識も彼女の中には確かにあった。
「社会の課題を解決したい、という思いが強くて、最初から自分には商業的なものが向いていることに気付いていたので、高校卒業後は芸大ではなく美大、つまりアートではなくデザインを選びました。ただ、それを高校の友達とかに伝えても理解してくれると思っていなかったので、学校の中では“学校バージョン”の自分として楽しんで、外にはまた違う自分がいる、という感覚がありました」
自分が何に向いているのか、興味を持っているのか。一方で、社会における役割はどこにあるのか。そして、その時々でどう振る舞うのが正解なのか。彼女はその全てがクリアに見えていた。まるで自分というパーソナリティとは別に、全体を俯瞰する神の視点を持ち合わせているかのようなスタンスだ。
大学は、地元神戸にある美大のファッションデザイン科へ進んだ。周りの学生は国内外の「ブランド」に熱を上げている中で、彼女はどこか斜に構えているところがあり、セレクトショップで買った当たり障りない洋服を身につけて通っていた。
「あまりにクラスで浮いているから、近くにある別の大学の学生だと勘違いされたこともあって。私自身、『ブランドのタグはついているけれど、コレクションラインじゃないでしょ?』とかって平気で言っちゃう、嫌なやつでしたね(笑)。もちろんブランドやデザイナーの思想に共感することはあるんですけど、ファンとして媒体の洋服を買う習慣がなかったんです」
授業のプレゼンでも、建築や小説、哲学などの本から”硬め”の要素を引用することが多かった彼女は、クラスの中で異色だったという。多くの学生がデザインの細部に懲りたがる中で、そこまで文脈を重視するタイプも珍しかったのだ。
そんな彼女は次第に、写真や哲学にものめり込んでいく。卒業制作では、「他人の中の自分の顔」というテーマのもと、印画紙を作る際に使用する「エマルジョン」という薬品を用いて、モノクロ写真を現像する際の原理を布の上で再現した作品を発表。作品は見事に学科最優秀賞を獲得し、兵庫県立美術館など2つの美術館で展示されることに。「商業的なデザイン」を志していた彼女が、大学最後のタイミングで王道の「アート作品」を作ったのには、ある意図があった。


*写真は九冨さん提供
「将来は商業的な道に進むことを心に決めていたので、大きなアート作品を美術館に展示するチャンスがあるとすれば、卒業制作が最初で最後だろうと。それともうひとつ、学校の中で目立ちたい思いもありましたね、正直。最後の花火をどう打ち上げようか、うーん服だと周りと差別化できない、よし縦2メートルの作品を作ったら注目されるだろう! みたいな感じで。だいぶ戦略的でした(笑)」
その時々でやるべきことをやる
そのあと新卒では、40年続く老舗の革メーカーに企画担当として就職。時代はファストファッション全盛、だがそこの会社は創業以来一度も広告を出したことがなく、「シンプル・ミニマル・コンテンポラリー」というコンセプトと、商品の質だけで40年間黒字を伸ばし続けてきた。その根底にある「思想」に、彼女は興味を持っていた。
「そこは、気付いたら隣の席の人が入れ替わっているような、いわゆるオーナーのワンマン企業。社員には奉公みたいな期間があって、デザイン画を100回書き直させられたり、社長に毎朝お茶を淹れなきゃいけなかったり。私がそれを耐えられたのは、どこかの時点で起業をすることを決めていたから。仕事がどんなにつらくても、自分の中ではあくまで過程だったんですよね。当時の私のクライアントは会社なので、そこで自分のクリエイションに固執しても仕方がないと思っていました」
その会社には5年間在籍し、2017年に独立すると、代官山に下着のセレクトショップ「タイガーリリートーキョー(Tiger Lily Tokyo)」をオープン。そこでは自身が共感できる、ジェンダーや色の既成概念にとらわれないブランドを主にヨーロッパから集めた。同時に、お店を起点として、まさに鴨居羊子さんが下着を通じて社会にメッセージを発していたように、女性の正直な気持ちにアプローチしたかった。映画や小説が「女性が当たり前に我慢している」描写に溢れているような状況は、一刻も早く変えるべきだと、強く感じていたのだ。

*写真は九冨さん提供
また当時、#MeToo運動がアメリカを中心に盛り上がり、同時にステレオタイプな女性像に対する疑問も噴出していた中で、「自分がやろうとしていることは時世にあっている」という状況判断も下していた。それに、自分の「思い」だけでは事業を継続することはできないので、専門書を読みあさって経営を学んだ。
「そういえばいま振り返ると、幼少期にファッションへの興味を掻き立たせてくれたのも、事業のきっかけを与えてくれたのも、美大時代の課題で引用元に使用していたのも、経営を学んだ先も、すべて『本』でした。鴨居さんの自伝がまさしく、自分が疑問に感じたことって、たいてい先人も同じように問題意識を持っている。だから、良書を辿ることで、自分が”いまやるべきこと”がクリアになるんですよね」
2019年からは、ノンワイヤーのランジェリーブランド「モンべべリリー(Mon Bebe Lily)」をスタート。同じころ友人の投資家から出資を受け、今度はオンライン販売も強化しはじめた。これまでそういった大きなターニングポイントがいくつかあったが、本人は「日常業務の延長ですから」というようなテンションで、過去の決断をサラッと振り返る。
そもそも、20代で経営者になることに対する不安はなかったのだろうか。
「いったん会社というハコを作ってしまえば、自分の立場が社長だろうとスタッフだろうと責任は一緒じゃないですか。今だって、自分が代表格ではありますが、同時に一社員でもあって。税金を払って会社を存続させるために、このくらい商品を売らなきゃいけないっていう計算式があるだけで、恐怖はありません。会社時代には、7〜8人のチームの中で50店舗分の企画管理を担当していました。そこでミスを犯したらスタッフ全員に迷惑がかかるし、取引先の信頼も失ってしまう。そのときのプレッシャーとたいして変わらないんですよね」
おそらくこの先のことも、学生時代のころと同じくまわりに言い触らすことはしないだろうが、虎視淡々と見据えてはいるのだろう。「次の目標は?」という質問に対する彼女のこの回答を聞けば、そう思わざるをえない。
「このまま頑張る、です」