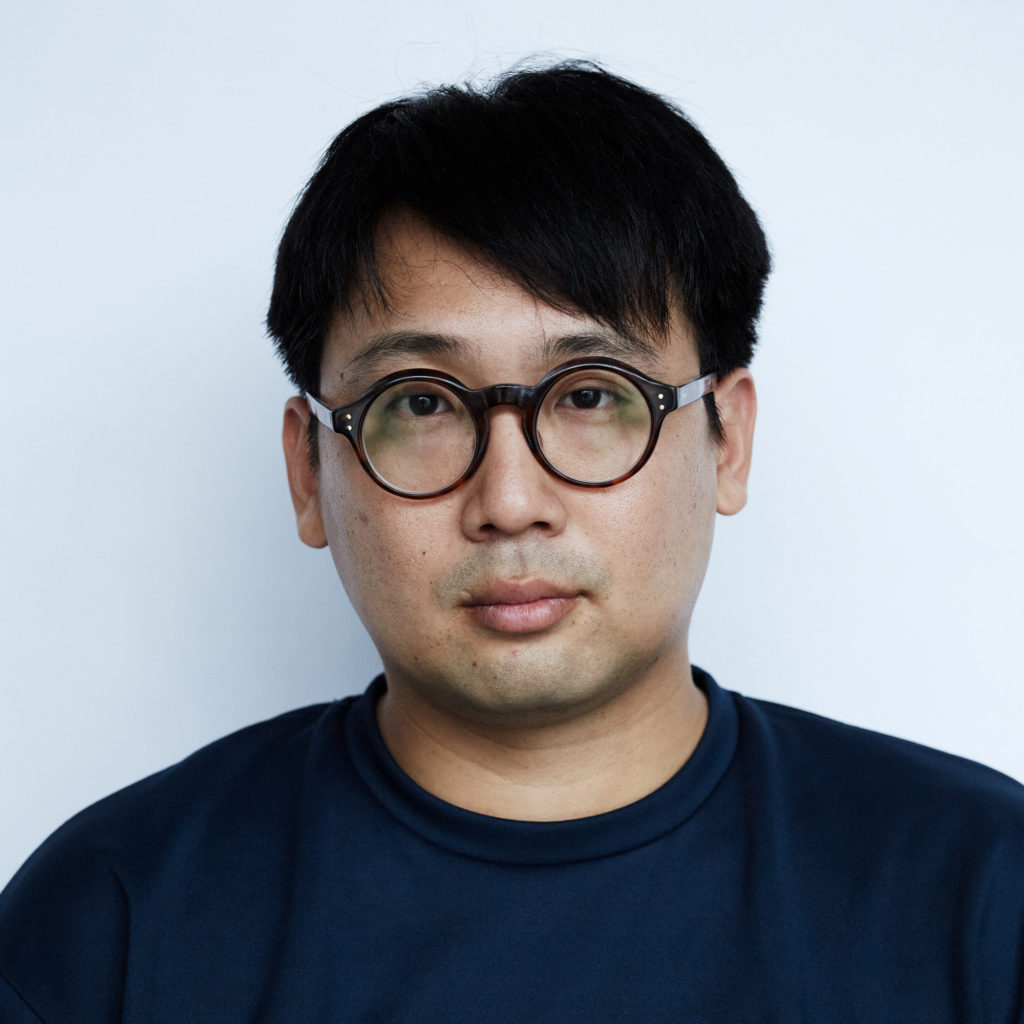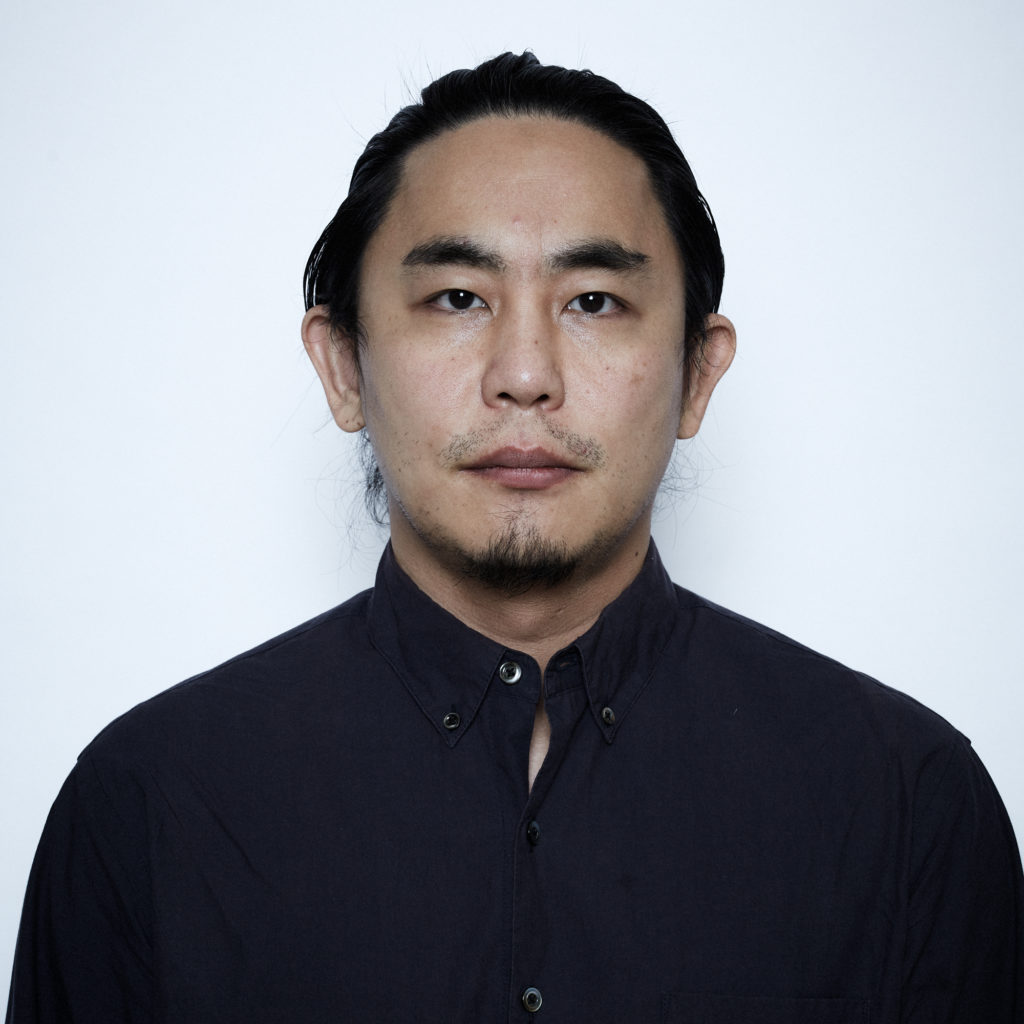企業や個人のお店などから依頼を受けて、“映画館ではない場所”に映画観賞のための空間を作るプロジェクト「キノ・イグルー」を手がける有坂塁さん。これまで、上野の国立博物館や恵比寿ガーデンプレイスの広場など、「ここに大きなスクリーンを持ち込んだら最高だな」という夢のようなシチュエーションで映画上映会を多数主催。上映後には、有坂さん自ら作品を解説するトークショーも必ず行われ、映画とはこんなに楽しいものだったんだ、と改めて気づかせてくれる。
有坂さんのひとつの特徴として、本人は人の何倍も作品を観てきた紛れもない「シネフィル(映画通)」であるにも関わらず、そのマニアックさをひとつも表に出さないところがある。かといって、ミーハーな映画ファンというわけでもない。ただただ、シチュエーションにぴったり合った映画を選ぶ、その精度においてとことんプロフェッショナルなのだ。なぜ個人の好き嫌いを超えた地点で映画と関わることができるのか。また、その熱量の源はどこにあるのか。今回は、彼の独特な「映画愛」に迫る。
シネフィルに対する憧れと違和感。
自称「社交的な映画オタク」こと有坂さんは、19歳まで映画をたった2本しか観ていなかった。10代で何かしらエポックメイキングな映画と出会い、そこから一気にシネフィルの世界へ足を踏み入れる人も多い中で、はっきりいって有坂さんは遅咲きである。
「小学生のとき連れていってもらった人生初映画は『グーニーズ』。自分もあそこに登場する少年たちと同じくらいの歳だったから、ファンタジーというより自分もあの中にいるような気がしました。当時、自宅近くに空き家があってそれまで気にも留めていなかったのが、映画を観たとたんそこに財宝が眠っているんじゃないかって、友達と一緒に忍び込んだりして(笑)」
田舎町・グーンドックを舞台に繰り広げられる冒険劇に惚れこんだ有坂さんは、「もう一度観たい!」と母親に懇願したが、「せっかくだし違う作品を」ということで、今度は「E.T.」を観ることに。だが、「E.T.」の姿形に恐怖を覚えてしまい、映画にまったく入り込めなかった。小学校ではサッカークラブに入って外を走り回っていたので、暗闇の中でじっとしているのも苦手だったのだ。彼は「もう映画なんか観るものか」と強く心に誓った。すべてはあんな恐ろしいモンスターを主人公にしたスピルバーグのせい、と有坂さんは笑う。
実際、そこから19歳まで一本も映画を観ることはなかった。当時は今と違って毎日のようにテレビで映画が放映されていたので、よほど堅い決心だったに違いない。そのかわり、中高ではプロを目指してサッカーに打ち込んだ。
「うちは母子家庭だったのですが、『好きなことを見つけてとことんやりなさい』というのが、毎日いそがしく働く母の教育方針でした。だから、大人になって会社で好きじゃない仕事をする、っていう選択肢自体が頭の中になかった。そういう環境もあって今も伸び伸びやれているんだろうなと。それと母は世代的にオードリー・ヘップバーンや『サウンド・オブ・ミュージック』に夢中で、子供にも音楽とか映画を好きになってほしかったみたいですね」
SNSなどで有坂さんの発信を追っていくと、「映画をオープンなものにしたい」という思いがヒシヒシと伝わってくる。その原点は、人生3本めに観た『クール・ランニング』という作品にあった。冬季オリンピックにジャマイカのチームが初出場する実話がベースとなった本作は、「あのカットの連なりに深い意味があるんだ」とか「あの俳優の表情が絶妙なんだ」なんていう含蓄とはまるで無縁の、最近ではめずらしいくらい真っ当なコメディ。有坂さんも例にもれず、本作のラストにある「スポーツの大事なところは勝ち負けだけじゃない」というメッセージに涙した。だが、そういった牧歌的な感想を、映画史に精通したシネフィル(映画通)は受け付けようとしない。
「その当時の彼らは、『クール・ランニング』や『アルマゲドン』、『ノッティングヒルの恋人』のような作品は『映画じゃない』というわけですよね。かつて僕はレンタルショップで働いていたんですが、その時に一緒だったメンバーがまさにそうで。もちろん僕も、シネフィルにしか作れない売り場に憧れていた。でも、好きなものを既存の価値観で否定されるうちに、シネフィルに対して違和感を持つようになったんです」

芝公園での上映会。写真は有坂さん提供。

初島での上映会。写真は有坂さん提供。
好き嫌いを超えたところで。
有坂さんは『クール・ランニング』を観て以来、映画のことなら何でも知りたいと貪欲に行動していた。当時付き合っていた彼女に連れられて映画館の魅力にハマり、そこからは自分一人で毎日通いだす。最初はトム・ハンクスとかウィノナ・ライダーのようなスター目当てで足を運んでいたが、恵比寿でウディ・アレンの『ブロードウェイと銃弾』を観てからは、カメラの後ろにいる「監督」に意識がいくように。そこから、パンフレットなどに掲載されているウディのインタビューを読みあさり、今度はそこで言及されている映画をチェックするようになって、フェデリコ・フェリーニ(「映像の魔術師」の異名を持つイタリアの映画監督。1993年没)やイングマール・ベルイマン(スウェーデンの至宝であり、20世紀を代表する映画監督の一人。2007年没)のような巨匠にまで手を伸ばしていく。
ではなぜ、有坂さんは映画というフォーマットにそこまでのめり込んでいったのだろうか。他のエンターテインメントやカルチャーと比べて、何が彼の心を動かしたのだろうか。
「双子の弟として生きていると、四六時中『似てる〜』とかって茶化されるから、人から見られることが当たり前になるんです。自分が受け入れるしかないとはわかりつつ、怒りのおさめどころも分からなくて、電車移動する時は兄と違う車両に乗ったりして……知らず知らずのうちにストレスをためていました。そんなときに『クール・ランニング』を池袋の映画館で観て、これは自分と映画だけの世界じゃないかと。まるで新しい居場所を発見したような気持ちでした」
それにしても、シネフィルから趣味の拙さを指摘されたときに、自分の心でそれをはねのけることができる人は稀有なはず。たいていの人は、そこで権威に屈してしまうか、映画自体から離れようとするだろう。有坂さんの外見には朴訥とした雰囲気が漂っているが、その中心部には、屈強なボクサーのパンチを受け続けてきたサンドバッグのように、どんな外圧にも耐える強力な「芯」があるようだ。
それはずばり、映画そのものに対する強烈なリスペクトだ。
「昔は、『おれは断然これ!』って好みを言語化できないことがコンプレックスでした。でもあるときから、『ああ、自分はそういう人間なんだ』と理解できて。僕は世界一映画に”甘い”んですよ。自分の美意識で観るんじゃなくて、どんな映画でもその中に入っちゃう。物語が最悪だとしても、『なんでこのシーンにこの音楽なんだろう?』って別の視点から考えてみるんです。探せばかならず何かはあるはずだから」
「映画がある日常」へのアプローチ。
映画のどういう部分を見ているか、それは十人十色だ。ひとつのアート作品として鑑賞する人もいれば、ストーリーラインを追う人もいる。それが、いま自分が抱えている悩みに答えなり癒しなりを与えてくれた場合は感動するだろうし、逆に『パルプ・フィクション』のような一般的に評価の高いものでも、観るタイミングによっては「?」が浮かぶだけの可能性もある。つまりどんな作品であれ、それがきっかけで個人の人生が変わったことに対して、シネフィルが否定する必要はどこにもない。その余計な圧力さえなければ、みんなが当たり前に自分の好きな映画の話をする世界が実現されるかもしれない。有坂さんが2003年にキノ・イグルーを始めた理由も、長年かけて醸成されてきた映画業界の閉塞感を打破したかったからだ。

上映後のトークイベント。写真は有坂さん提供。
彼は現在、移動映画館の他に、その人にあわせた作品を選ぶ映画カウンセリング「あなたのために映画をえらびます」を定期的に行っている。そこには、日常に余白をつくることが難しくなった時代背景が大きく関係していた。現代は1日で2時間を割くにもハードルが高いので、多くの人が「せっかく映画を観るんだったら絶対に後悔したくない」と考える。だからといってAIのレコメンド機能を頼りにしていると、同じようなジャンルの映画しか観ることができず、いずれ飽きて映画から離れていってしまう。人は、自分の外側に心に響くものを発見できてはじめて、映画それ自体の魅力を知ることができるのだ。
「たとえばパリだと、一昔前はどのエリアにも小さな映画館があったから、みんな自宅から歩いていけるわけですよ。家族でごはんを食べてお風呂に入ったあと映画を観にいく。東京だとさすがにリアリティがないんですが、だったらせめてコミュニケーションベースで日常の中に映画があればいいなっていう」
有坂さんは、「映画って良いよね」という根源的な熱量でキノ・イグルーのプロジェクトを推し進める。そもそも、彼からしてみれば、「あの映画、つまんなかったね〜」と言い合うのも楽しい行為なのだ。

北海道の上映会にて。写真は有坂さん提供。
映画を通して自分を再発見する。
有坂さんが映画のカウンセリングを行うときには、ひとつのルールを設けている。それは、お客さんに何の役柄も演じさせないこと。たとえば、ある女性からは「子供を連れていきたい」と相談されたことがあるが、それだと彼女が「お母さん」を演じることになってしまうので、そのときは丁重にお断りした。自分自身もまだ気づいていないパーソナリティを掘り下げないと、その人に合った最適な映画は出てこない。中には、長いあいだ蓋をしていた話を開陳して泣き出した人もいたという。もちろん本人はプロのカウンセラーではないが(何だったら、プロの映画人と言われることにも拒否反応を示す)、コミュニケーションの方法論として映画を用いていると考えれば、活動のすべてに合点がいく。
「ちょっと大きなことをいうと、みんなが各々の中にある“当たり前の自分”にたどり着いてほしいんです。今は情報量の多さも影響して、奥底にある自分と社会的な自分がどんどん乖離している。でも、自分が主催する上映会で映画を観ているときの表情を見ていると、性別も年齢も立場も関係なく、その人自身が剥き出しの状態になっているんですよ。あの光景がより広い範囲で実現すれば、世界はもっと平和になるのになって」
有坂さんはいま映画を外側から眺めるポジションに立ちながら、決して歩みを止めず、シネフィルたちも納得せざるをえない状況をコツコツと作り上げている。インスタグラムでは毎日映画を紹介し、定期的にトークライブを発信し続けている。また、仕事で会った人からは「好きな映画」をかならず訊くようにしていて、22年も前からそれをノートに書きためている。やはり、この芯の強さは半端なものではない。
真正面から喧嘩をしかけて業界の中に居場所を作ることもできなくはないが、有坂さんはそういう性格からほど遠い。彼はシンプルに、誰かと映画の話をするのが好きなのだ。