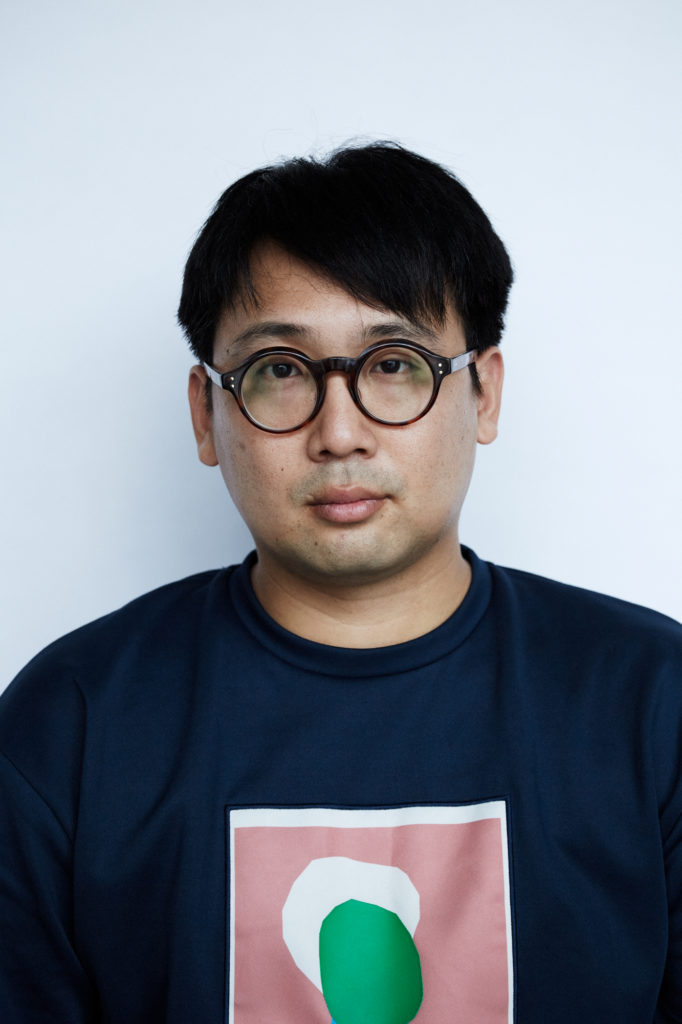今回のスミスは、食の分野で新しい領域を開拓し続けるシェフの森枝幹さん。メインシェフを務めた代沢の割烹「サーモンアンドトラウト」では、亜熱帯化する日本を東南アジアの一部として捉えた上で、南国のテイストを加えるなどその土地性を強く意識した料理を出していた。そしてその実験精神は、昨年パルコ渋谷の中にオープンした「チョンプー」でもいかんなく発揮されていて、「面白いタイ料理はもっとあるよ」という提案を、あくまでカジュアルな形でもって投げかけている。
「サーモンアンドトラウト」も「チョンプー」も、食通だけではなく音楽やファッションが好きな人たちの間でずいぶん話題になっていた。彼の料理を口にした人たちはみな一様に「すごい」なのか「新しい」なのか「やばい」なのか、とにかく「美味しい」の先にある感覚を表すための言葉を探しはじめる。やはり、シェフとして紛れもなくスペシャルな存在。今回は、そんな彼が「いま考えていること」にスポットライトを当ててみた。
料理に自由をもたらすために
「チョンプー」は、欧米では当たり前の「屋台とは一線を画す、レストランクオリティのタイ料理」という存在を日本で浸透させる狙いのもとスタートした。オーストラリアで修行するところから料理の世界へ足を踏み込んだ森枝さんは、世界のスタンダードを日本にどのような形で持ち込むか、を実践し続けている料理人でもある。
「オーストラリアでは人種と感覚がフラットで、キッチンにも自然といろんな国の人たちが混在していました。お店に関しても、屋台料理を出すお店もあればハイエンドなレストランもあって、それらが切磋琢磨しているのが格好良いなと。色々あって良いじゃん、を再確認できた。日本と違って新しい国なので、変に守るものがないんですよね」
とはいえ、日本で強い違和感を感じていたわけでもない。単一民族の国で価値観が固定してしまうのは致し方ないこと。それぞれ国の成り立ちは異なるわけだし、正解は一つではない、というのが彼の見方である。そうやって多様性を海外で実感したからこそ、森枝さんも料理に関して己の価値観を押し付けるつもりは毛頭なく、あくまで「こういうものがあるよ」と提案するに留めている、という。

アウトサイダーからの視点
またそれは、父・卓士さんからの影響によるところも大きい。卓士さんはかつて紛争などを取材するフォトジャーナリストとして活動しており、しばしば海外の情報を仕入れるために現地へ赴いていたが、一般の人々の暮らしについては正しい情報を日本に持ち帰ることが困難だった。しかし彼は次第に、民の暮らしとその中で生まれる文化に興味を持つようになり、あるときから「食」へ活動の舞台を移した。そこで得た「みんないろんな事情があるんだから、それをちゃんと配慮した方がいいよ」という教えを、森枝さんにもよく話して聞かせていたのだ。
さて、「サーモンアンドトラウト」なんかは特に、どこか日常の中の非日常という趣がある。彼は、既存の枠組みの中で精度を極めていくのではなく、料理に対する視点をズラすことで、「美味しさ」の許容範囲を押し広げている。
「僕がよく利用している未利用魚(サイズや漁獲量の関係で流通されなかったもの)が美味しくない理由は、魚自体のポテンシャルの問題というよりも、単純に雑な扱いを受けているから。つまり、食材の管理や火の通し方における”許容値”をきちんと守りさえすれば、十分に美味しく調理できるんです」
森枝さんは、「和食」の概念にまったく囚われていない。日本の伝統、というと絶対に死守せねばいけないもののように感じられるが、よくよく考えてみてほしい。和食も時代ごとに幾度もアレンジされていて、いまみんなが「和食」だと認識しているものは、原型でもなければ、未来永劫変わらないものでもない。例えば、江戸時代までは醤油も一般に流通されておらず、冷蔵庫が登場するまで山間部で刺身は食べられなかった。
森枝さんはそういった食の歴史も参照しながら、実際にオーストラリアから帰国後は京料理の老舗「湖月」で修行を積んでいる。だからこそ、説得力をもって「王道以外」を発信できるのだ。

「料理の世界では、自分が修行してきたお店のやり方に固執してしまって、独立後も視野が広がらないケースが多い。同世代の友だちに連絡もとらせず何年もお店に閉じ込めて修行させる、という話をいまだに聞くことがありますが、そんな人がいきなり社会に出て通用するわけがない……いやでも、その純粋培養が逆に面白くなる可能性もあるかな……情報を一切遮断して、逆方向に進化するというか。いま自分で話しながら両方の可能性を思いついてしまいました(笑)」
森枝さんはこうやって話している中でも、どんどん新しいドアを開けていってしまう。冷静に食業界の「外」から観察しているからこそ、素材と同じく人材も「どう活用するか」に意識がいくかもしれない。最近では、プレイヤーという立場を維持しながら、下の世代の才能を引き出す役割にまわることも考えている、という。
そういえば、「サーモンアンドトラウト」では合計4年間キッチンに立っていたが、その合間を縫って海外で新しい食材やネタを探したり、国内の若手や海外のシェフらと一緒にイベントを開催したりしていた。プレイヤーでありながら編集者的な性質も強いようで、プロデュースワークも実に巧み。レモンサワーで知られるゴールデン街の新星「The OPEN BOOK」にしても、有名パン屋さん「365日」が出したカフェ「二足歩行 coffee roasters」にしても、フードカルチャー誌「RiCE」にしても、彼はオーナーや編集長からのアイデアを受けて、具体的なイメージをいくつも形にしてきた。
「どうやらその人が求めているものを掴むのが得意みたいで、『ああ、それなら海外のどこどこで同じようなものがあるよ』ってスッと出せるんです。でもね、逆に僕はとにかく面倒くさい性格なので表に出ない方がいい(笑)。いつも俯瞰でものを見すぎてしまって、それが自分で嫌になることもあるんですよね」
これから実現させたい世界とは
自分自身には何の執着もないけれど、一人一人のシェフはこだわりを持っていてほしい。みんなが自分みたいな編集者気質になったらダメでしょう。そう自嘲する森枝さんは、「良い料理」についてもかなり幅広く捉えているよう。彼にとって、然るべき場所に然るべき理由である料理であれば、それはすなわち「良い料理」なのだ。森枝さん自身も大きな仕事に関わる中で、必ずしもシェフとしての個性を毎回爆発させるわけではない。
結局のところ、森枝さんは料理を通じて何を実現させようとしているのだろうか。その質問をぶつけてみると、本人からは「世界平和っぽいことは考えていますけどね」という答えが返ってきた。お互いの「しょうがない」が理解できれば、譲り合える部分もある。そのひとつの過程として、東南アジアの料理に対する「安いもの」という思い込み、未利用魚に対する勝手な「まずい」という印象、そういった固定概念をポップに変えていきたい。それは、いま世界中で取り沙汰されている持続可能性の話にもつながってくるだろう。
「例えば、地球温暖化の影響もあって漁獲量が減っている現状に対して、何ができるのか。みなさん色んなアイデアがある中で、僕は自分のお店でブラックバスを使うことを考えました。ブラックバスといえばかつて食用としてアメリカから日本に持ち込まれたものの、最近ではそのイメージがなくなってしまった魚。でも、こっちが『お店で使いたい』とお願いすれば、産地の人たちは何とか対応してくれるんです」
いま地球上で持続可能性について真剣に考える余裕がある人は、先進国の中の、さらに富裕層に限られる。そこで何とかあがいているジェスチャーをすれば稼げるだろうが、そこに興味はない。だったら、自分が好きなものに囲まれてひっそり生きていくほうが良いかもしれない。大きく、希望的にやりたいわけでもない。もちろん料理や食材の感動は追い求めているが、それもパターンが見えてきてしまっている……。
「何かは感じているけれど、同時に感じなくなってきた。それでも、動くことをやめられないんですよね」
コンセプチュアルな食への入口は低く、逆に出口は高く設定する。全員がその核心とメッセージを理解できるわけではない。森枝さんとしては、現実的に難しいこととは分かりつつも、みんなを何とか理想郷へ連れていきたい。この、諦観と希望が入り乱れて、しかし確実に希望のほうがわずかに上回るバランスこそが、森枝さんの魅力である。