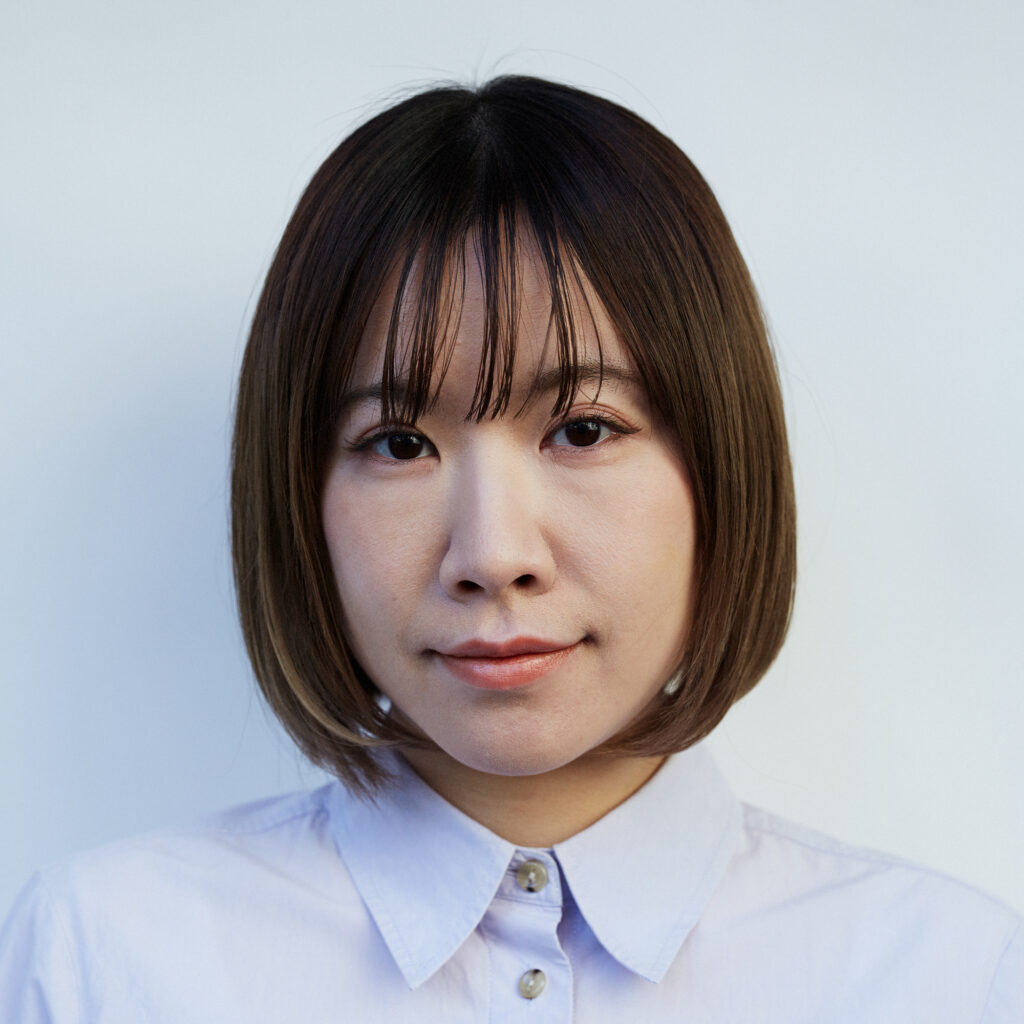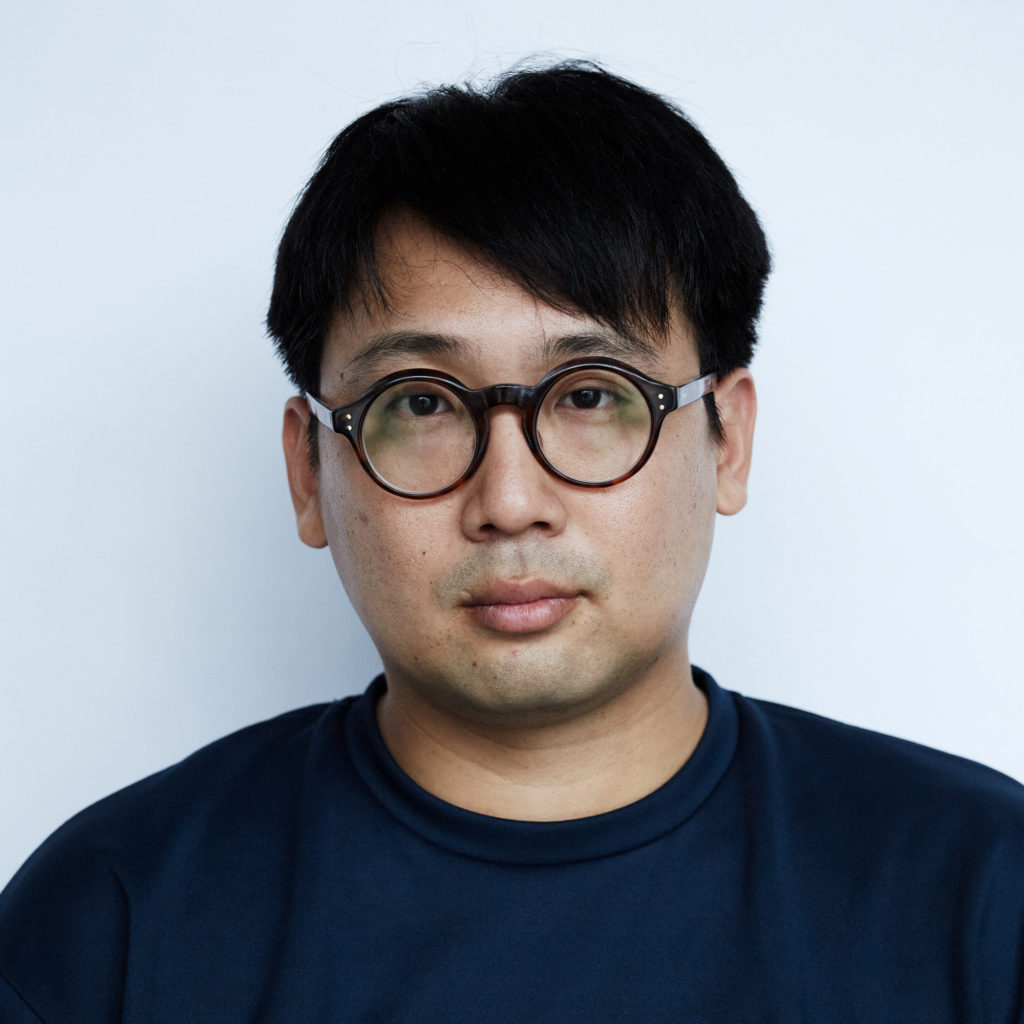今回のスミスは、奥渋谷でチーズ専門店「CHEESE STAND」を営む藤川真至さん。2011年にオープンした同店は、開店直後から有名レストランで扱われ、またテレビ番組でも紹介されて瞬く間に人気となり、休日に行列が絶えない状況がしばらく続いた。チーズ専門店というとラックに多種多様なチーズが並んでいる絵を思い浮かべるかもしれないが、開店当時はモッツァレラとリコッタの2種類のみとラインナップを厳選、今でも「渋谷でチーズを作り、出来立てを提供すること」を重視している。
今でこそ若手のスタッフたちが仕込みを行なっているが、つい最近まで藤川さんが朝3時前に起床し、都内の酪農家からトラックで運ばれてくる生乳を受け取って、店内の工房でチーズづくりを行っていたという。またコロナ禍の最中は、自身のnoteでお店における数々の挑戦(ECメニューの開発や自社メディアなど)を報告しながら、もがき続ける姿をあえてそのまま見せた。今回は、生産者と経営者、2つの役割を抱えながら、「都内発のフレッシュチーズ」という前代未聞の分野にいどむ彼の“ひたむきさ”に迫る。
貪欲に学び続けてきた人生
藤川さんのチーズづくりにおけるルーツは、イタリアのスイスの国境付近にあるトレンティーノ・アルト・アディジェ州にある。高校卒業後、大阪外国語大学に通っていた彼は、5年生のときバックパッカーとして世界中を旅する中で、偶然ナポリで見つけたピザ屋さんで働くことに。そこでモッツァレラの工場を見学する機会があり、出来立てのチーズの魅力を初めて知る。そこから今度はトレンティーノ・アルト・アディジェにある牧場でチーズ作りを学ぶ、という経緯だ。
「その頃の1日といえば、朝6時に起きて、牛の世話をして、冬にむけて薪を割ったり、山の芝刈りをしたり……そこでは修行というよりもただ手伝わせてもらった、という感じです。かなりの重労働で、チーズを食べられることは尊いんだと気付きました。でも大変とは言いつつ、働くこと自体は楽しくて。バックパッカーをやっていたことも含めて、『新しいものごとを知りたい』という思いが強かったから。そこからまた、『新しい価値を作りたい』という欲も出てきました」


イタリア修行時代 *写真は藤川さん提供
彼は物心つく前からチーズが大好きな少年だった。今でも忘れられないのは、休日の昼間に出てくるピザトーストの味。高校では部活に入らず、かわりに家でたまに料理を作っていた。ただ、身内にシェフがいたわけでもないし、特別な英才教育を受けていたわけでもない。当時参考にしていたのは、ビストロSMAPのレシピ本『ビストロスマップ完全レシピ』。独学で料理の楽しさを知っていく。
イタリアから帰国後、名古屋のレストランで4年働き、料理にとって素材がいかに大切かを学んだ。そのとき彼は、いずれ自分のお店では駅ナカにも進出しているスープストックのように、「質の良い料理で多店舗展開」がしたいと考えていた。世の中にはファーストフードが溢れている中で、安心安全な素材をできるだけ多くの人に届けたい、という思いがあったのだ。
そこで次は経営やマネージメントを学ぼうと考え、2008年に有名ビジネスマンが手がけた赤坂のドーナツ屋さんにマネージャーとして参加。出店や催事にも携わりながら経営全般を学ぶ中、2011年に東日本大震災がおきる。そこで彼は、インフラとしての店舗を優先するがあまり、ときにアルバイトを店舗に一人で立たせてしまうなど力の入れどころを誤ってしまう。このとき、自分の思いで先走るのではなく、お店全体の良い雰囲気を作り出すことが重要だと痛感した。
なお藤川さんのnoteでは、上記のエピソードも含めて過去のトライ&エラーが驚くほどあけすけにされている。例えば、『CHEESE STAND』からどんどん人が抜けてしまう時期があった。美味しいチーズを届けたい思いは変わらないし、お客さんも順調についてきたが、仕組みがうまくまわらない。では、過去の偉人たちはどのようにして危機を乗り越えてきたのだろうか。今の自分には何か足りないのか。次はこう改善してみよう……そこには、心の葛藤が生々しい温度で刻まれている。まさに「終生勉強」を地で行く人だ。
「経営の勉強には、中小企業診断士やMBAの教材を使っていました。お店を出す際は起業塾にも参加しましたし、学ぶことに対しては貪欲。その理由を考えてみると、自分はずっと周りに対する劣等感があったんですよね。僕は大学時代ラグビー部に所属していたんですが、同期はみんな大企業に就職していく。彼らには負けられないな、自分の力で上がっていくしかない、って」
職人として、経営者として。
当初、『CHEESE STAND』は多種多様な人に開かれたお店にしたいという思いから、店内で使われるメニューやロゴの書体は世界でもっとも多く使われているヘルベチカに統一、店内のBGMも社長自ら選曲しないなど、できるかぎり自分のキャラクターが表に立たないように配慮していた。中である程度のコミュニティが出来上がっているせいで、一見さんに「入りにくいな」と思われるのは、まだ許容できる。こちらがいくらオープンな姿勢を打ち出していたとしても、そう感じてしまう人がいるのは仕方がない。しかし、わざと排他的な空気をかもしだして、それをブランド価値にするようなお店にだけはしなくなかった。
だが、仕組みや労働環境の改善を重ねていく一方、そんなお店の理想系もまた、彼の中で変化し続けているようだ。
「お店の次のフェーズとして、僕じゃなくスタッフの個性がもっと表に出ても良いのかなと考えるようになりました。だから今年の8月、自分たちでチーズペーパー(CHEESE PAPER)っていうタブロイド紙を作ったんです。基本の姿勢はオープンで誰でも入れるんだけど、中にはコミュニティがしっかりある、その良いバランスを実現させたい。ロールモデルの一つとしては、よなよなエール。名前が全国に知られていて、デザインがポップで、ファンに長く深く愛されている。また、定期的にフェス(よなよなエールの超宴)を主催してコミュニティを可視化させていますよね。クラフトビール界の中でも特殊な存在じゃないですか」
この思いの変化には、彼自身のパーソナリティの移り変わりも影響している。『CHEESE STAND』開店以来、手仕事の微調整によってチーズの味が激変することを体感するうちに、彼の中では職人的なパーソナリティの比率が高まっていた。美味しくないものを出したくない抵抗感が、日に日に増していったのだ。それに伴って、チーズ職人を雇って自分は経営に専念しようと思っていた起業当初から、多店舗展開という方向性自体にも変化が生じていた。
現在、藤川さんの構成比率は、職人が60パーセントで経営者が40パーセントだという。『NARISAWA』(ミシュラン二つ星レストラン)のような、かつては雲の上の存在だった偉大なお店がチーズを使ってくれたこともある。だったら自分は素材を作る側としてもっと突き詰めよう。彼はそう心に決めたのだ。

「自分の性格的にはたぶん職人なんだと思います。戦略的にやれるわけでもないし、数字にも弱い。職人はものづくりを掘り下げていく作業じゃないですか。1日の何時間かはそこに向き合って、空いた時間に経営のことを考えたり、人に会ったりしています。自分の中では完全に棲み分けが明確なので、2つの役割が葛藤しあうことはありません」
藤川さんは、ある程度お店が軌道にのった今でも、自己評価がすこぶる低い。だから、他人から教えを請うことも厭わないし、異なる考えも受け入れられる。そもそも人を嫌いになるということがない。
彼が意識を向けているのは自分のお店だけではない。2019年には、国産チーズを本格的に根付かせるために、仲間と共に一般社団法人「日本チーズ協会」を立ち上げるなど、社会的な責任に対しても真摯に向き合う。その源泉はいったいどこにあるのか。
「スポーツでもビジネスでも、何かで優勝したことってあります? 僕にはまだその経験がないんです。だから、勝ちたい……なんていうと大げさなんですけど(笑)。大学でラグビー部にいたころ、毎年かならず東京外国語大学との直接対決があって、いつも負けっぱなしだったのが3年生のときやっと勝てた、その高揚感が頭に残っていて。勝って嬉し涙を流している、あの感覚……だからお店もできるだけ長く続けていく中で、いつかチーズ界の頂に立つ日を夢見ているんです」
かつて、肝心の牛乳が仕入れられなくなるピンチを迎えたこともあった。そのときは都内の酪農家さんや日本乳業協会に掛け合ってなんとか切り抜けた。また、お店がオープンする直前にはイタリアで出会ったチーズ職人が急遽来日できなくなってしまい、かわりに自ら全ラインナップのチーズを作ったこともある。
本人いわく、いつだって3歩進んで2歩戻る感覚。それは、相当タフな体と精神がなければ実践できないはず。スクラムを組んで歯を食いしばりながら巨大な相手に立ち向かう藤川さんの表情が、ふと目に浮かんだ。