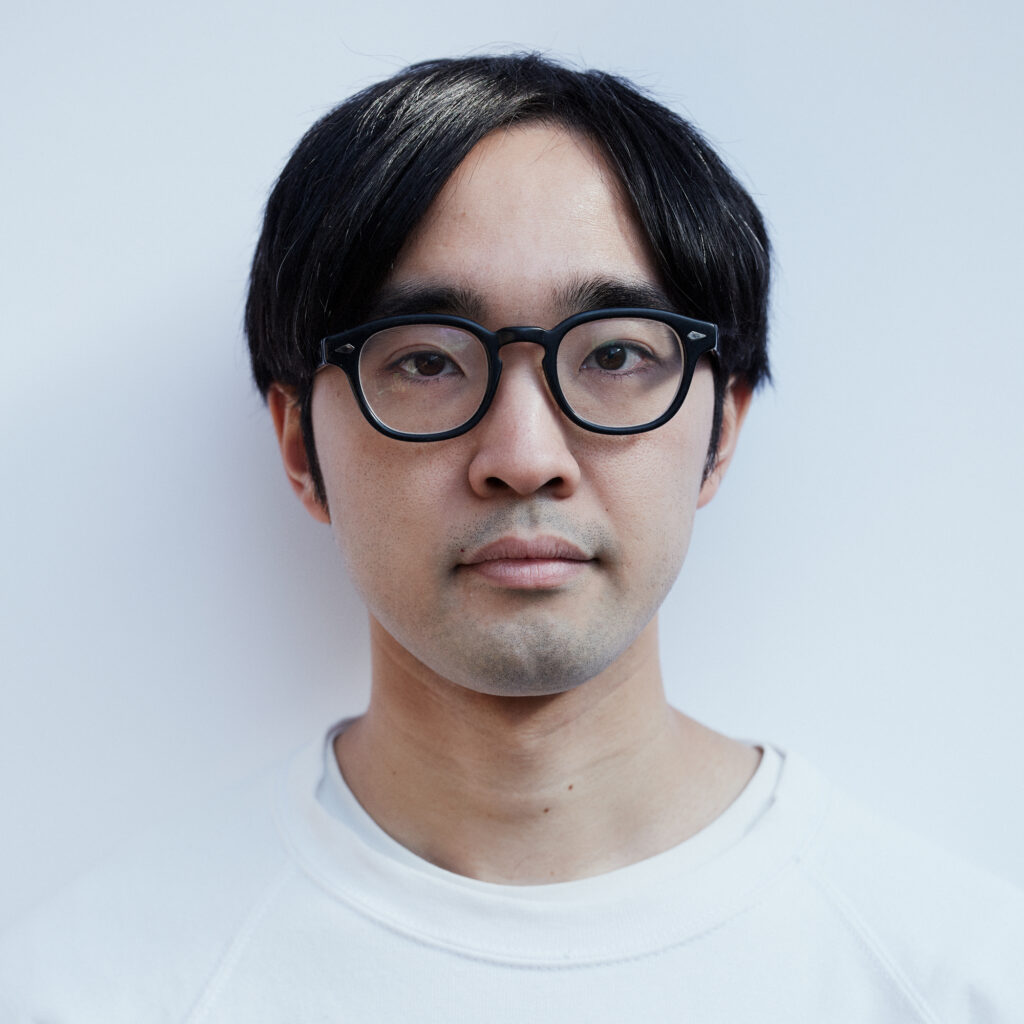今回のスミスは、外資系のコンサルティング会社で働きながら、ステンレスストローの提供を軸に「のーぷら No Plastic Japan」として環境問題に取り組んでいるノイハウス萌菜さん。ドイツで生まれ、イギリスで10代と20代前半を過ごした彼女は、日本に移り住んでから、ある「オーガニックレストラン」で店内で飲む水のカップが使い捨てにされていたことに疑問を感じ、そこから環境問題全般に興味を広げていった。プロジェクトを立ち上げて約2年、これまで個人や飲食店などを相手に1万本以上を販売してきた。また、販売した際の包装紙には、自分の家にある新聞紙や過去のカレンダーを使用するなど、細かい部分まで環境への配慮を徹底している。
一方、「のーぷら」の活動がファッション雑誌『VOGUE』で紹介されるなど知名度を増していく中でも、彼女は会社に在籍し続けている。そこには、彼女なりの明確な狙いがあった。環境問題に対する個人のスタンスや思いは、どうしても「エコ」という言葉で一括りにされがちだが、今回は彼女が「ステンレスストロー」という手法を編み出すまでの経緯から、彼女独自の哲学を読み取っていく。
環境問題に興味を持ったきっかけ
ドイツで生まれたノイハウスさんは、6歳から24歳までの年月をイギリスで過ごす。イギリスの高校では、必修科目として「アート」「音楽」「心理学」「歴史」からどれか一つを選択する必要があるという。最初はアートに興味を持っていた。しかし、実際にクラスをとってみると、「描きたいから描く」という考えしか持ち合わせていなかった彼女は、リファレンス(引用元)やコンセプトありきの世界観に肌が合わなかった。かわりに選んだのは、心理学だった。
「私は誰かと話しているときに『なんでこの人、いまこれを言ったんだろう?』って考える癖があって。腹の内を探るとかそういう意味ではなくて、単純にその背景とか根本を知りたいっていう。大学でも心理学を専攻したんですが、特に興味を持ったのは、言葉と心理について。例えば、ロシアでは水色の中にも二種類あるらしく、それはそれぞれの色を指す言葉が存在するからなんですね。だた、日本には『水色』という一つの言葉しかないから、そこに微妙な違いがあったとしても認識できない。要はそこに言葉がなければ、概念も存在しないわけです」
「なぜそうなっているか」、ものごとの成り立ちが気になって仕方ない。そもそも環境問題に興味を持ったきっかけは、子供のころに「紙は木からできているんだよ」と聞かされて半ばトラウマになったこと。彼女はそこで「木を切り倒すことになるなら紙は使いたくない!」と言い放ち、絵を描くときは自分の「手」をキャンバスに使うように。そこから、いま手元にあるものが何からできているのか、どのようなプロセスを辿ってここへやってきたのか、「成り立ち」を自然と気にするようになったのだ。

小さいころは極度にシャイだったという。*写真はノイハウスさん提供
大学卒業後は、「色んな業種の会社と関わってみたい」という思いのもと、大手のコンサルティング会社を就職先に選ぶ。そこのクライアントは大企業がほとんどで、実際に関わることでしか見えない内情が思ったよりも多かった。
「とある軍需企業とお仕事する機会があったんですが、正直最初はあまり良いイメージがなかった。でも実際にご一緒する中で、その会社が最先端のテクノロジーや教育にも力を入れていることを初めて知ったりして、白か黒かで判断できることはないと痛感したんです。また、厳しい状況の中でも“良いこと”をやろうとがんばっている人はいますよね。そういった経験を経て、だんだん全体の構造に目がいくようになりました」

大学時代のノイハウスさん。*写真はノイハウスさん提供

イギリスから日本へ越してきたころ。*写真はノイハウスさん提供
自身のメッセージを「どう」伝えるか
彼女が取り組んでいる環境問題に関しても、やたらと大手を批判したがる人も多い中、彼女は「良い部分をサポートしたほうがいい」という考えを持っている。もちろん本人もすぐにその考えに至ったわけではない。「のーぷら」の活動を開始する前は、自身のSNSに「オーガニックカフェにきたけれどストローがプラスチックだった」と正直な思いを投稿したこともあった。当初は「できていないところ」に目がいきがちで、その気持ちがあったからこそステンレスストローのアイデアが生まれたのも事実だが、今は「できているところ」を積極的に見せることで、ポジティブなサイクルを意識的に作っているという。
誰かを悪者にして済む話ではない。みんなの生活に細かな原因があるわけだから、問題はみんなで一緒に解決していく他ない、というわけだ。もちろん、彼女の中にもまだ「怒り」はある。とにかく不必要なプラスチックの使い捨てをなくしたい。伝えたいメッセージがここまで明確だからこそ、「伝える方法」にはかなり細心の注意を払っているのである。
「海外は素晴らしい、日本はダメだ。これでは伝わるものも伝わりません。実際にかつての日本には、量り売りや“もったいない”のカルチャーが定着していた。今は環境対策の面で欧米に遅れをとっているかもしれませんが、日本はいったん何かが流行ると適応する力はあるので、希望はあるんです。考えるべきは、そこまでどう持っていくか。すでにイギリスではプラスチックのストローは使われていないわけで、私が掲げている目標はぜんぜん非現実的じゃないんですよ」

のーぷらのステンレス製ストロー。*写真はノイハウスさん提供
一方で、彼女はフォロワーたちをけっして「啓蒙」しないように気をつけている。インスタグラムのダイレクトメッセージで「どの商品を使うべきですか?」と訊かれたときも、彼女は明確な答えを返さなかった。彼女は単に、環境問題について考えるきっかけを与えたいのだ。
「まだ色々と迷われている方に『この人がやっているから正解なんだ』と思われるのはどうも……。私だって当然のように迷うし、いきなり方向性が変わるかもしれないし、そこまで責任は持てません(笑)。理想は、フォローしてくれている人たちの間で勝手に議論が進むこと。私の役割はあくまで『種まき』なんです。ステンレスストローをツールに使っているのはまさしくそういう意図で、私の活動を起点に各々の活動が展開されていけばいいなと」
ステンレスストローのアイデアが生まれる前、当初は世界中からエコな商品を集めたショップを開こうと考えていた。ただ、いきなりお店を作るのはリスクが大きすぎるので、様子見のためにまずストローを作りはじめたという。これが意外に、自分のコンセプトを伝える最適な手段、つまり誰にでも分かりやすい「種」だということが徐々に分かってきた。
さらに、ストローというアイテム選びにも背景がある。世界中でエコが叫ばれ始めたタイミングで、どこもかしこもエコバックを作りはじめたため、「一人が何個もエコバックを持っている」という何とも皮肉な現象がおきた。要は、すでに家にあるものをわざわざ「エコ仕様」に作り替える必要はない。その中で、ほとんどの家になくて、お店がすぐ切り替えられるものは何かを考えた結果、それがストローだったのだ。
二足の草鞋を履く理由
何を伝えるかに加えて、どう伝えるか……ふと、誰もが中身を読みたくなるような新聞の見出しづくりに腐心するジャーナリストの姿が頭に浮かんだ。環境問題に取り組んでいくにあたっては、社会全体を見渡さんとする広い視野が必要となる。彼女は自身のポジションをあえて一つに固定しないことで、その視野を獲得しようとしているようだ。
「会社を辞めないのは、まさにリアルな社会を知るため。環境問題に取り組んでいるときは心が落ち着く反面、周りのコミュニティで起きていることだけが常識になってしまうんです。『知り合いはみんな私のストローを持っている。あれ、もういいんじゃない!?』って(笑)。環境問題と一般社会をつなげる役割ができたら、それが本望かもしれません」
彼女いわく、ひとつひとつの決断に明確な理由を持ちさえすれば、性質の異なる立場を兼任することは難しくない。そちらの方が自身のメンタルも安定するようだ。何か理不尽なことが起こったときも、色んな世界の常識やルールに触れていれば、いちいち自分がそちらに引っ張られることもない。また現在、ストローをそこまで欲していない人が勢いで購入するのを防ぐため、「のーぷら」としての広告は一切出していないのだが、そのスタンスを貫くことができるのも、会社に所属していて生活費の心配をしなくて済むおかげである。
少し前までは、何にせよ一つのことに打ち込むことが美徳とされた。しかし、今は手段ではなく目的が問われる時代になった。静かなトーンではあるが「だってそうじゃないですか」という風に確信めいた彼女の口ぶりをみると、その事実を実感せざるをえない。
「私は企業に勤めていて、結婚して子供も産んで……ある意味では突っ込みどころのない人生を送っている。みんなが期待する道を無意識に歩んできて、他人より余裕がある身だからこそ、切実な人たちのかわりに環境問題について発信するべきだと思うんですよね。自分が出入りしている環境問題のコミュニティ内にも、熱心に活動しているのにメディアに取り上げられない人は大勢います。だから、もし私が今後テレビなんかに出る機会があれば、自分の話だけではなくその人たちが草の根でやっている活動を伝えたいんですよ」
ここまで自身のポジションに意識的で、なのに「やらなきゃやらなきゃ」と焦っている様子は全くない。モットーは「明日できることは明日に」。とはいえ、一見ハードにみえる二足の草鞋生活で、本人の体や精神に無理が生じることはないのだろうか。
「その時々でフォーカスしている部分も違いますし、同じタイミングで全てのことに全力を尽くすわけではないので、無理はしていません。苦労ってたいてい自分の中から生じるもの。『他人にこう思われているのかな』とか、『自分はこういうところが足りないかも』とか、考え出すとキリがない。誰だって批判されるポイントは持っていますが、逆に熱心なサポーターもどこかにはいるはずで。それを思えば、焦らず着実に社会へ働きかける、これしかないんですよね」